
マネジメント層に組織全体を通した視点を。部署を横断した連携を促進。
コンテキストの力で生活者とブランドを結びつけるデジタル広告プラットフォームを提供している外資系企業、GumGum Japan(ガムガムジャパン)株式会社にマネジメントベースを導入いただきました。
今回、マネージャー層および次期マネージャー候補を対象に実施した背景や目的などお話を伺いました。
GumGum Japan株式会社
マネージングディレクター セルビー健三 様(写真:左)
オフィスコーディネーター 暮地岩 柚子 様(写真:右)
一人ひとりのJob Descriptionが明確だからこそ起こりやすい、「サイロ化」の壁を超えていくために
マネジメントベース編集部(以下、編集部):
管理職、マネジメント教育に関するこれまでの取り組みを教えてください。
セルビー様:
GumGumは2008年にアメリカで設立され、日本法人は、2017年に主にセールスや運用サポート、カスタマーサクセス機能を担う形で立ち上がりました。
現在、日本では約20名の体制で事業を展開しております。
弊社の業務は、広告配信が中心であり、営業や運用、カスタマーサクセスといった部署にわかれて業務を進めていきます。
こうした体制の中で、顧客情報やキャンペーンの進捗状況、デジタル広告の市況の変化などを部署を超えて共有し、価値提供につなげることが重要になる中、部署間の連携やコミュニケーションにおいて、十分に機能しきれていないと感じる場面も少なくありませんでした。
これは、私が2023年9月に日本のマネージング・ディレクターに就任し、日本市場を担当するようになった当初から感じていた課題のひとつです。
外資系でよくある話かもしれませんが、GumGumでも「Job Description」がきっちりと決められているため、 各々に与えられたロールはそつなくこなして機能的には果たしているものの、どちらがその業務を行うのかが分かりづらい事象が起こったときに、誰がそれを行うのか、自分の役割ではない、など宙ぶらりんになってしまうようなことも発生していたのです。
その結果として、コミュニケーションコストが非常に高く発生してしまい、アウトプットに影響が出ることもありました。
そのため、マネジメント層には、部署の役割や機能を理解し全うするのはもちろんのこと、組織全体 を通しての視点を持ち行動するようになってほしいと考えていました。
アメリカ本社では、マネジメント層向けの研修コースやe-Learningが提供されているのですが、日本でビジネスを進めていく上では、文化や言語の違いから、日本チームにとっては適応しづらい部分が多いと感じていました。
そのため、日本独自で自分たちにあった研修を探す中で、マネジメントベースに出会いました。
座学だけでなく、ゲームで学ぶからこその意味がある

編集部:
マネジメントベースをご導入いただいた背景や目的はなんだったのでしょうか?
暮地岩様:
今回、マネジメントベースのお話を聞いた際に、「マネジメントをシミュレーションできるゲーム」だと伺い、とても興味を持ちました。マネジメントの視野を広げられると感じましたし、コミュニケーションもより活発にできるのでは、と期待していました。
実施にあたっては、各部署のマネージャー3名に加え、今後マネージャー職を目指すメンバーを中心に集めて研修を行うことに決めました。
セルビー様:
私自身、 これまでのマネジメント経験の中で、講演などを通じて学ぶ機会はあったものの、受け身のレクチャー形式が中心だったこともあり、印象に残りにくく、実践にも繋がりにくいと感じていました。講演やセミナーでは、「実際に自分が経験した」という実感がなかなか持てなかったので、客観的な視点を持ちながら、自分の手を動かして学べるゲーム型シミュレーションには、大きな意味があると感じていました。
また、事業として生き残っていくためには、共通のゴールに向かってチーム全体で動いていくことが欠かせません。ただ、現実には「木を見て森を見ず」のような状態で、俯瞰してビジネスを捉えられていないと感じる場面もありました。
マネジメントベースのゲームをプレイする中で、日々の課題を一人で解決するのではなく、チームや部署をまたいで連携しながら取り組む、という考え方へと意識をシフトしてもらえればという想いがありました。
自分の部署だけで物事を考えてしまうと、本来は部署間で連携すれば解決できたことも、解決できなくなる可能性があります。また、明確に線引きされていることで、かえって摩擦が生まれてしまうケースもあります。
だからこそ、「もし自分がマネージャーだったらどうするか」という視点を持って、全体を俯瞰するような目線で考えるきっかけになればと思っていました。その点では、今回の取り組みはうまくいったのではないかと感じています。
また、外資系とはいえ、従業員はほとんどが日本人であることもあり、研修においては日本のコミュニケーションスタイルや現場に合った内容が求められます。、ヒアリングを通じて、パーソナライズされた形で研修を提供いただけたのも、良かったポイントの一つです。
自身が見ている視座・視点を見直すきっかけに
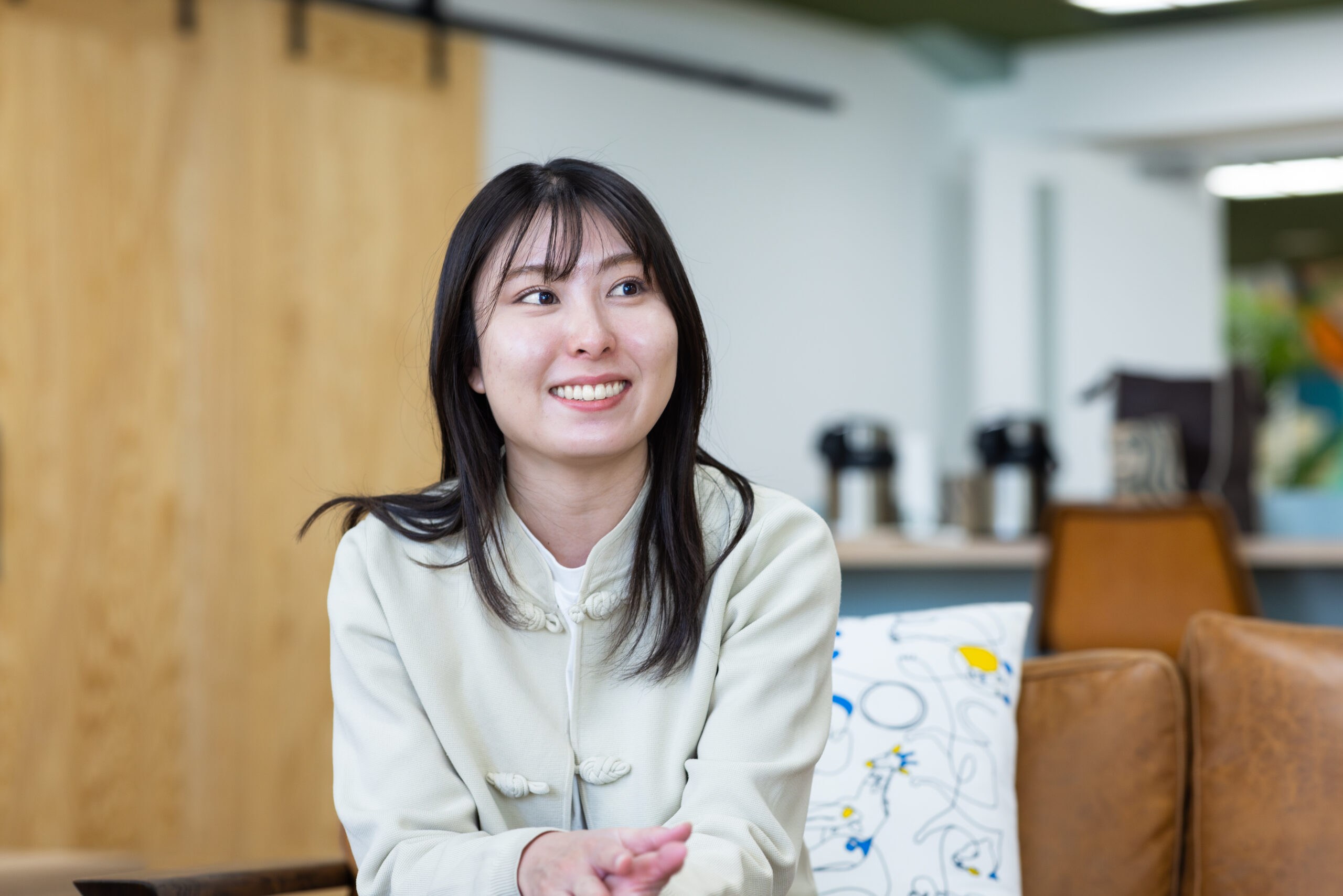
編集部:
実際に研修を実施してみていかがでしたか?
セルビー様:
研修を受けていた従業員の反応としては、ポジティブなものしか上がってきていません。 休憩中にも、仕事の課題について自然と会話が生まれていたり、普段は見えにくい個々の課題についても、個人的にコメントをもらえたりしていて、少しずつ視点が変わりつつあるなと感じています。
受講したメンバーの中には、私や他のマネージャーのマネジメントに対して、疑問や意見を持っていたメンバーもいたと思います。ただ、研修後には「日々いろんな課題が出てくる中で、マネジメントは一筋縄ではいかないということがわかった」といった声も上がっていて、実感を伴った理解につながったのではと感じています。視点の変化だけでなく、「組織についてポジティブに考えるきっかけになった」というコメントも印象的でした。
また、今回はあえて異なる部署やポジションの人たちを同じチームにして研修に取り組んでもらったことで、自然にコミュ ニケーションが生まれ、他部署の人がどういう立場で物事を見ているのか、ゴールまでの考え方がどう違うのか、といった点を体感できたのもとても良かった です。
実際に、他部署の視点を踏まえて考えられるようになってきましたし、同じチーム内だけでなく、他部署と連携してプロジェクトに取り組もうとする動きも見られるようになってきました。
暮地岩様:
私から見て印象的だったのは、マネージャー陣が多く集まっていたテーブルで、最終的にマネージャー候補のメンバーがゲームに勝っていたことです。現マネージャーたちにとっても、自分のマネジメントのやり方を見直すきっかけになっていたと思います。
また、ゲームの後に取り組むワークシートにも、それぞれが非常に具体的に、しかも「明日からの仕事にどう活かすか」といった実践的な内容をしっかり書き込んでいて、学びの多さが伝わってきました。
さらに、優先順位の考え方が根づいてきたのも良かったです。
課題が複数出てきたときに、どこから手をつけるべきなのかを考える意識が見られるようになってきたのは、大きな変化だと感じています。
マネジメントベース研修全体の設計としても、座学・ゲーム・ワークシートのバランスが非常に良く、どれかに偏ることなく統計されていたのが良かったです。 そのおかげで、活発な意見交換やチームプレーも見られたのでよかったです。
組織がより活性化され、全体最適的なコミュニケーションを

編集部:
今回の取り組みを経て、見られた変化はありますか?
セルビー様:
マネジメントベースを含めた研修の取り組みを経て、コミュニケーションコストの部分はかなり改善されてきていると感じています。
日本法人では現在、3期連続で2桁成長を続けており、案件数も大きく増えています。メンバーを大幅に増員することなく、事業を成長させられているのは、組織全体の動きが良くなってきたことの表れだと思います。
今後は、部署にとらわれず、もっとフラットに会話ができて、みんなが毎日来たくなるような会社でありたいと常々思っています。実際、出社を週5で義務づけているわけではないのですが、この数カ月は、積極的にオフィスに来るメンバーも増えていて、そうした変化が見えてきたのは本当にうれしかったです。
また、以前は「何かあればいつでも相談してください」と伝えていても、なかなか声をかけてもらえる機会が少なかったのですが、最近は「ちょっと相談したいことがある」といった声や、気軽な質問が自然と増えてきていて、良い変化を感じています。
社内調査でもこれまで、コミュニケーションや働き方に関する改善の余地があることは見えていましたし、私自身もそこには意識して取り組んできたつもりです。ただ、当時はその取り組みがどれだけ届いているか、実感しにくいところもありました。
「これからは、もっとリッチなコミュニケーションを育てていこう」という思いで進めてきた中で、そうした前向きな変化が少しずつ見えてきたのは、素直にうれしく感じています。
今後の取り組みとNEXERAに期待すること
編集部:
今後のNEXERA、マネジメントベースに期待することはありますか?
セルビー様:
まずは今回のセッションで得たことを日々の業務で実践してみて、その後、社内で振り返る機会を設けたいと考えています。実践の様子やメンバーの反応を見ながら、次のステップとして、これからマネージャーを目指すメンバー向けに、あらためてセッションを実施していただければと思っております。
暮地岩様:
私としては、組織で出てくる課題に対しては、適切な研修を通じてしっかり向き合い、解決を目指していきたいと考えています。そして、メンバー一人ひとりが着実にスキルアップできる環境を提供していきたいです。
外資系ということもあり、引き続き英語のレッスンなどは提供していきますが、それに加えて、ソフトスキルも学べる環境を今後ますます充実させたいと思っています。外部講師など、異なる視点を持つ方々からの学びを取り入れることで、新たな変化が生まれ、これまで挑戦できなかったことにもチャレンジできるようになると期待しています。
そうした取り組みを、短期的なものにせず、長期的にPDCAを回しながら、組織全体の底上げにつなげていければと考えています。
NEXERAへの期待としては、今後もさまざまなテーマに応じたプロダクトが増えていくとうれしいです。特に、弊社としては「チームビルディング」に特化したプログラムに期待しています。仕事への向き合い方やスキルの土台となる、多様な価値観や人との関係性を強化するような研修に力を入れていきたいと考えています。
外資企業の良さと日本企業の良さをミックスした組織づくりを

編集部:
今後の管理職、マネジメント層の活躍に向けてどのような取り組みをお考えですか?
暮地岩様:
弊社は外資系の日本法人ということもあり、どうしても結果主義の文化が強く、ややドライな側面が出やすいと感じています。
だからこそ、外資系の合理性と、日本企業が持つ人とのつながりや温かさのような文化をうまく組み合わせて、両方の良さを取り入れた組織をつくっていけたら理想的だと思っています。
個人主義的に、与えられたことだけをこなすのではなく、チームとしてしっかりコミュニケーションを取りながら、意見を出し合えるような関係を築いていきたいです。
一言で言えば、「仲の良いチーム」を目指すことで、より良いアウトプットにもつながると考えています。今後も、そうした文化づくりに取り組んでいきたいと思います。
